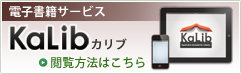Vol.73 No.4 July 2025
原著・臨床
昭和大学病院における最近9年間の血液培養分離菌とASTからの助言内容の推移をみた多変量解析
1)昭和医科大学医学部内科学講座臨床感染症学部門
(旧 昭和大学医学部内科学講座臨床感染症学部門)
2)昭和医科大学横浜市北部病院内科系診療センター感染症内科*
(旧 昭和大学横浜市北部病院内科系診療センター感染症内科)
3)昭和医科大学薬学部臨床薬学講座感染制御薬学部門
(旧 昭和大学薬学部臨床薬学講座感染制御薬学部門)
4)愛泉会日南病院内科
5)昭和医科大学病院臨床検査室
(旧 昭和大学病院臨床検査室)
要旨
昭和大学病院および昭和大学病院附属東病院では,抗菌薬適正使用支援活動の一環として,血液培養陽性者回診を行い,2015年の4月からは中心メンバーと方法を固定して行ってきた。この間の血液培養分離菌と助言内容の推移を検討し,助言率と助言実行率に注目して報告する。
2015年4月から2024年3月までで初回血液培養陽性の6,201例を調査した。患者背景,血液培養分離菌,原因感染巣,診療科,助言率,助言実行率の推移について,標準最小2乗法を用いて一部多変量解析を行い評価した。
調査期間中の年次推移で患者数はやや増加したが,患者背景に大きな変化はなかった。多変量解析において診療科では救急診療科(P<0.0001)が減少,血液培養の初回分離菌ではStreptococcus pneumoniae(P=0.0013)が減少,原因感染巣としては不明(P<0.0001)が増加するなどそれぞれいくつかの傾向が認められた。菌種ごとの集計では原因感染巣に偏りがあり,菌種同定が原因感染巣推測の一助になると考えられた。多変量解析で調整した助言内容では,抗菌薬選択(P=0.0116),抗菌薬の用法用量(P=0.0004),診断(P<0.0001),ソースコントロール(P<0.0001),その他(P=0.0019)で助言数の減少傾向を認めたが,微生物学的検査では変化を認めなかった。抗菌薬選択の細分類では,開始(P=0.0126),追加(P=0.0407)は減少傾向,変更,中止では変化は認めなかった。抗菌薬の用法用量の細分類では,減量(P<0.0001),血中濃度測定(P=0.0524;有意ではないが)では減少傾向で,統合,増量または併用では変化は認めなかった。助言実行率は単変量解析を行ったが,その他(P=0.0354)で増加した他には変化は認めなかった。
抗菌薬適正使用支援活動は,長期に継続していると教育効果が働き,助言を行わなくても実行できる環境が整ってくる。しかし,専門的助言を必要とする部分は継続して残っており,今後も地道に継続して活動することが重要と考えられる。
Key word
antimicrobial stewardship, bacteremia, fungemia, appropriate use, acceptance rate
別刷請求先
*神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央35-1
受付日
2024年10月25日
受理日
2025年2月10日
日化療会誌 73 (4): 309-321, 2025